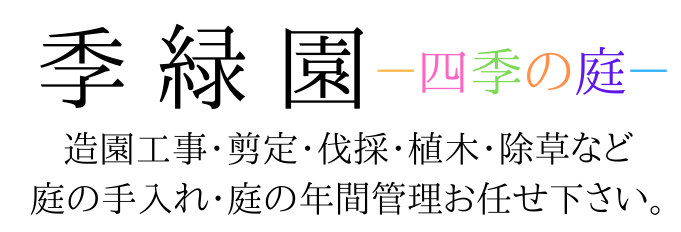2025年08月09日

先日、真夏の猛暑日に訪れたミクロネシア・マリアナ諸島のサイパン。ここでは日本と異なる穏やかな熱帯の気候や植物に触れることができ、同時に日本の夏の気温上昇や猛暑日増加、気候変動や環境について改めて考えさせられる大事な機会になりました。
サイパンの気候と日本との違い
サイパンは年間を通して平均気温が約27〜28℃と安定しており、強い日差しはあるものの海からの貿易風(北東の風)が抜けて体感は意外と真夏でも快適です。日本のように「猛暑日(35℃以上)」になることはほとんどなく、島全体に熱がこもらないため、屋外でも心地良く過ごせるのが印象的でした。
日本の夏はアスファルトやコンクリートなどが熱を蓄えるヒートアイランド現象が深刻ですが、サイパンでは木々の緑や貿易風(北東の風)の影響で気候が穏やかです。


日本・千葉県での真夏の気温(輻射熱を含む)値を測定しました。
おおきな木々で直射日光を遮る木陰(気温35℃)とコンクリートやアスファルトの直射日光のあたる場所(気温51℃)では、16℃の気温差が確認されました。これは、森林だった場所が失われ人工的に開発されたコンクリートやアスファルトの場所では広範囲に気温上昇が起きることを示しています。

サイパンと日本の植物の病害虫発生の違い
サイパンでは、日本では珍しい鮮やかな熱帯植物が多く見られます。庭の植栽や街路樹も日本とは異なる種類で、人工的に植えられた植物でも病害虫の被害が少ないのが特徴です。
一方、日本では外国から多様な植物が輸入・流通しています。その豊かさは魅力ですが、外国の益虫がいないことや在来の益虫が対応できないこと、高温多湿の環境が重なるため病害虫の発生が多くなるようです。
サイパンを含むマリアナ諸島(CNMI)では在来植物を守るために外来種の持ち込みに制限があり、自然の生態系のバランスを大切にする姿勢が感じられました。


マリアナ諸島・サイパンの代表的な植物
1. 南国を象徴する代表的な植物(観光・生活・文化でよく目にするもの)
プルメリア(Plumeria spp.):中南米原産。白・ピンク・黄色などの香り高い花を咲かせ、レイや観光シンボルとして親しまれる。
ハイビスカス(Hibiscus rosa-sinensis):鮮やかな大輪の花が咲き、庭園・ホテル・公共施設に広く利用される。観光客に「南国の花」として人気。
ココヤシ(Cocos nucifera):果実は食料・飲料に、幹や葉は建材や屋根材として利用。生活文化に深く根付いた重要な植物。
モモタマナ(Terminalia catappa):海岸沿いや街路樹として多く植えられる。大きな樹冠で日陰をつくり、葉や種子は薬用・食用にも用いられる。
モクマオウ(Casuarina equisetifolia):糸のような枝葉をもつ常緑高木。海岸の防風林や街路樹として植えられ、独特の枝垂れた景観をつくる。



バナナ(Musa spp.):古くから定着している果樹で、日常的な食材として広く栽培される。
2. 伝統的な在来植物(マリアナ諸島固有種・広域在来種)
マリアナパンノキ(Artocarpus mariannensis/dugdug):デンプン質の果実は伝統的な主食で、文化的にも重要。
マプニャオ(Aglaia mariannensis):香りのある花をつけ、森林の重要な構成種。
アトト(Syzygium thompsonii):幹や枝から直接花や果実をつける「カウリフローリー」の特徴を持つ。
アガテラン(Eugenia palumbis):赤い果実は食用になり、鳥や動物の食料源として重要。
ヨガ(Elaeocarpus joga):青い果実をつける希少な在来樹。
ガウサリ(Bikkia tetrandra):海岸の岩場に多い低木。白い大きな花が咲き、地域の自然景観を象徴。
ハリオトロピウム(Heliotropium anomalum):塩害に強い低木。砂浜や海岸に多く生える。
タロイモ(Colocasia esculenta)、ヤムイモ(Dioscorea spp.):古来より栽培されてきた伝統作物。
カッフォ’(Pandanus tectorius/タコノキ):葉は織物や工芸に使われ、果実は食用にもなる。
ウムム(Pisonia grandis)、ニヨロン(Cordia subcordata)、アハガオ(Premna serratifolia/ハマトウガラシ)、ヌヌ(Ficus prolixa/ガジュマル類)、ファダン(Cycas micronesica/ソテツ):在来森林や文化的価値を持つ樹木・植物。

3. 希少な固有植物(保護対象)
Serianthes nelsonii(ハーユン・ラーグ/トロンコン・グァフィ):マリアナ固有の巨大マメ科高木。絶滅危惧種。
Ochrosia mariannensis(ランギティ):石灰岩林の固有樹木。
現地の植物に対する価値観
サイパンでは、在来植物は文化的・生態的象徴とされ、地域のアイデンティティに深く根付いています。特にマリアナパンノキは食文化や伝承と結びつき、在来樹を育み保護する動きもあります。一方、観光業の影響で目立つヤシ並木など外来植物も多く、在来種保護と外来種の調和が地域の自然への考え方に反映されています。


サイパンと日本の気候変動:現状と今後の対策
サイパンでの海面上昇と珊瑚礁への影響
平均年約7.6 mm、2100年までに65 cm~最大2 m弱の上昇を予測しています。
沿岸地域の約80%が浸水リスクがあります。
マリンヒートウェーブ(海洋熱波)の頻度増加により珊瑚白化・死滅。2012~2018年で浅瀬の珊瑚被覆は3分の2に減少しています。


日本での気候変動の傾向
過去20年で夏季最高気温が上昇、猛暑日増加しています。
森林の保護や樹木の蒸散冷却作用、遮光、二酸化炭素吸収、酸素の発生効果がますます重要となっています。


-サイパンでの気候変動への今後の対策の一例-
マングローブや自然石垣による海岸防護
珊瑚再生プログラム・保護区整備
地域住民と連携した気候適応計画の推進 など
-日本での気候変動への今後の対策の一例-
都市計画でのグリーンインフラ導入(大木・透水性舗装)
庭や公園での樹木活用による自然環境再創造
エネルギー消費を抑えつつ植物の力を活かすランドスケープ設計 など
自然と共生する環境の大切さ
受粉を助けるミツバチがいなくなると作物も実らなくなるように、たくさんの生き物は互いに役割を持ち環境を保っています。
樹木は直射日光を遮るだけでなく、二酸化炭素を吸収して酸素を放出する、蒸散作用で周囲の温度を下げる。
風通しの良い大きな木の木陰に入るとエアコンが無くても快適に過ごせるのはこのためです。


樹木植樹の庭づくりと未来へのつながり
庭に計画的に配置を考えて樹木を植え、風が通る日陰をつくることは、景観だけでなく環境を保全し実用的快適性にもつながります。
近年、地球規模で進む気候変動は、日本でも猛暑日の増加や都市部のヒートアイランド現象など、日常生活に直結する影響として現れています。サイパンのように自然の緑と風が心地よさを生み出している環境と比べると、日本の都市部では人工的な構造物が熱を蓄え、快適さが失われつつあります。
これからの時代に、「樹木を植えること」は美観や景観づくりにとどまりません。森林保護や樹木の維持には大きな環境価値があります。快適で健康的な暮らしを支えると同時に、地域や社会全体の環境保全にもつながります。

樹木と二酸化炭素(CO₂)の関係と役割


1.二酸化炭素(CO₂)の吸収と炭素固定
樹木は葉の光合成により、太陽の光を使って二酸化炭素(CO₂)と水から糖を作ります。この糖は樹木の成長のエネルギー源となるだけでなく、木材や根、枝などの組織に炭素として蓄えられます。
光合成の化学式
6CO₂ + 6H₂O → 光 → C₆H₁₂O₆ + 6O₂
幹・枝・根・葉に蓄積された炭素は数十年〜数百年単位で大気中の二酸化炭素(CO₂)を減らす働きをします。
庭木クラスの広葉樹(樹高約10m)1本で年間数kg〜十数kgの二酸化炭素(CO₂)を固定
密集した森林では1haあたり年間数トン規模の二酸化炭素(CO₂)吸収
2. 樹木のそのほかの役割
環境調整
葉の蒸散作用で周囲の温度を下げ、体感温度を2〜5℃下げる
局所的に湿度を保つ
建物や道路の風を和らげる
空気・土壌の浄化
葉で微粒子や有害物質を吸着
落葉や根から有機物を供給し、土壌の栄養循環を促す
生物多様性の支援
野鳥や昆虫の住処になる
花や実は人間や動物の食料源
3. 人間活動による温室効果ガスとの関係
化石燃料や森林破壊で排出された二酸化炭素(CO₂)の約半分が大気中に残る
二酸化炭素(CO₂)は数十年〜数百年単位で大気に残り続ける
産業革命前:280 ppm → 現在:約420 ppm
二酸化炭素(CO₂)濃度が倍になると、地球平均気温は約3℃上昇すると推定
過去100年で平均気温は約1.2℃上昇
樹木1本の年間の二酸化炭素(CO₂)吸収量は人間1人の排出量のごく一部ですが、都市緑化や森林の保護は局所的・世界規模で二酸化炭素(CO₂)濃度上昇の緩和に役立つ効果があります。
4. 気候変動・地球温暖化対策としての樹木の役割 まとめ
樹木は単なる庭の装飾ではなく、二酸化炭素(CO₂)を吸収して炭素として長期蓄積、気温・湿度・風・空気の浄化、土壌の肥沃化、生物多様性の維持、自然の空調・浄化装置としても役立ちます。気候変動は遠い国の話ではなく、私たちの日々の暮らしとつながっています。木々や生き物は人間の活動による温暖化や環境変化を緩和する重要な役割を持っています。
「地球にやさしく快適に過ごせる屋外空間」を目標に庭や木々を維持管理し、皆様に喜んで頂きお役に立てる庭づくりを行ってまいりたいと考えています。


参考資料・出典
CNMI Climate (2016). Climate overview of the Commonwealth of the Northern Mariana Islands. NASA. Saipan Sea Level Rise Summary.
NOAA Tides &amp; Currents. Sea level trends at Saipan tide gauge.
U.S. EPA (2017). CNMI coral reefs: 2017 bleaching and 2012–2018 condition decline.
PIER, IUCN GISD. Casuarina equisetifolia (モクマオウ) – 防風樹としての利用と外来種リスク評価.
University of Guam Herbarium. Aglaia mariannensis and other native Mariana flora.
CNMI Invasive Species Council. Invasive species management in the Northern Mariana Islands.
気象庁. 気候変動監視レポート・ヒートアイランドの長期変化傾向.
環境省/東京都. ヒートアイランド対策に関する資料.
U.S. EPA. Urban Heat Island Mitigation Strategies.
IEA (2018). The Future of Cooling: Opportunities for energy-efficient air conditioning.
農林水産省「森林のCO₂吸収量」
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)
日本造園学会
国際連合気候変動枠組条約(UNFCCC)
UNFCCC公式サイト
気象庁「地球温暖化の現状」
日本気象協会「温暖化とCO₂」
(※本文中の一部データや体感値は季緑園での現場で観測した測定結果に基づいて作成しています。)